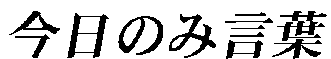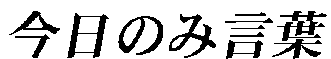イエスは、自分を正当化しようとしていた律法学者に「隣人とは誰か」と問いかけられました。これは今の私たちも問いかけられていることです。
では今の私たちにとっての隣人とは誰でしょうか。一般的に隣人と言いますと、自分の友人、知人など、自分を大事にしてくれる身近な人を頭に思い浮かべるでしょう。けれどもイエスは、別な箇所で「自分を愛してくれる人を愛したところで、どんな報いがあろうか」と言われました。つまりイエスの求める隣人とは、私たちの考えるような身近な人ではないということです。
私が子供の頃、同和問題というものがありました。近所のある地域は所得が低い貧しい家庭が多く住んでいました。そこに住む子供たちとは同じ小学校には通っていましたが、私の親もそうでしたが、「あそこの子とは遊んではいけない」とよく言われましたので、学校で会っていながらも仲良くすることはなかったように思います。このような見方というのは、子供ながらに差別と分かっていましたが、自分から何もすることはできませんでした。
実は、遊んではいけないというのは全くの偏見で、貧しい地域に住んでいるから悪いことをするとでも思っていたのでしょう。むしろ、その貧しい地域に住む人たちの方が偏見をもっておらず、そこに住んでいる一人のおばさんは、私が近所から来ているのを知っていても気前よくお菓子をくれたことを覚えています。
今、考えてみると、あのおばさんは、私にとって追いはぎに遭った人を助けたサマリア人のように思えます。おばさんたちは、サマリア人のように差別や偏見を持たれておりました。けれども自分たちをさける地域の子供に対して何の偏見もなく受け入れ、それも優しくかかわってくれました。これこそが隣人として相手を受け入れる姿勢です。
イエスが私たちに問いかける隣人とは、私たちにとってはすぐそばにいるはずです。しかし私たちが偏見や差別を持つかぎり、自分にとっての隣人が誰であるかは見えてこないのではないでしょうか。
NICCHI
今日記念する聖人、アシジの聖フランシスコは、聖書をライフワークの指針にしていた聖人です。(どの聖人もそうでしょうが…)もちろん今日の福音の箇所も繰り返し読んだことでしょう。
「律法(聖書)には何と書いているか。あなたはそれをどう読んでいるか」。「行って、あなたも同じようにしなさい。」このイエス様の問いと言葉を自分への問いと言葉として受け止めたに違いありません。そしてあのような生き方をするに至ったのだと勝手に想像します。
自分の「隣人」は誰か?どこにいるのか?と問うのではなく、自分自身が誰かの「隣人」になること。そして聖フランシスコは、隣人の「隣人」になることに努めました。きっとイエス様の「隣人」にもなろうと努めたのでしょう。身に受けた聖痕は、イエス様の「隣人」になることが出来た徴なのかもしれません。
福音書には、何と書いているのでしょう。それをあなたはどう読んでいますか?行って私たちも同じようにするように致しましょう。
mickey sdb