鶴岡教会(山形)・紐差教会(長崎)練成会
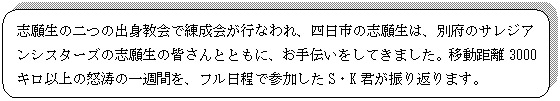
その時歴史が動いた
高二 S・K
2007年7月。わたくしS・Kと一部の四日市志願生&一部のサレジアンシスターズの志願生は、四日市志願院のエネルギーの源であるH・S君の出身教会である鶴岡教会でのサマーキャンプと、我ら四日市志願生の一人であるスーパーヒョロリM君の出身教会である紐差教会のサマーキャンプに参加した。そこで私は今から「私が勝手に作った皆さんの質問!」にお答えして差し上げましょう。私が何故、チョー大事な高校2年生の夏休みを削ってまで長期スーパーハードサマーキャンプに参加したのか!それは、そこに子供達の声があるから、そして、神様が僕らを呼んでいるからさ!!!
7月25日すいようビ。この日、私達は5時半にミサをした。この時点でウルトラスーパーハードである。そして車内で約12時間の道のりを走った。これまたウルトラスーパーミラクルハードである。☆とここで、他にも「ハード」と感じる時はあったのだが、何度も書くとけっこう字数が多いので、後の文章では書かないことにする☆そしてついに山口県!!?ではなく山形県!!!に着いた。そして僕らの冒険は始まるのだった。
山形県。わたくし東京出身者から見れば、そこはジャングルだった←ウソ。とにかく自然の香りが気持ちよかった←ん~。大自然で植えられたメロンは美味しかった←ホント。そして大自然で育った子供達は、クロマグロのようだった←マジで。そう、山形の子供達は止まったら死んでしまうのではないかと思うくらいチョー元気だった。なんせ朝5時ごろ起きてドッジボールを始めるほど元気な子供たちなのだから・・・。
山形キャンプでは何をやったかというと、司牧をしたのだ。そんなことは分かっている。私達はこの山形キャンプで、子供達に何を伝えることができたかということを聞いているのだ!それは、このキャンプでのテーマにもなっている「いのちは宝もの神様の贈りもの」にそって、私達は殉教者のことについて伝えた。各班ごとに劇を発表して、みんなで共に学びあった。そう、いのちとはみんなの為、そして神様のためにあるのだ。このキャンプではたくさんのことを学んだ。劇の練習では、けっこうてこずったところもあったりはしたが、みんなで頑張ることができた。ゲームでは、みんなで共に笑い楽しんだ。お祈りの時間、ロザリオや光の集いでは、心の中にある小さな灯を一心に見つめながら神様の声に耳を傾けた。そのようなごく普通の出来事の中で私達は輝いていたのだ。そこで仲間と共に、神様と共に過ごすことができた。そしてそれが生きることであり、いのちなのだ。そしてこのキャンプでの神様によるいのちが生きていたのだ。その時歴史が動いた。
7月29日。イガイト・スーパーマッチョイM殿の出身教会に着いた。そこには、ヤッパリ・ヒョロリM君のほかに、数人の四日市志願生とほぼ全員集合のサレジアンシスターズと合流した。そしてそこでバーベQをしたが、途中雨が降ってきたのでテーブルを中に入れたら雨がやんだ。もーなんということだろう。我々人間が雨にいじめられるなんて。ムスッ!!そんなことを言ってはいけない。世界には、心の貧しい人がたくさんいるのだから。それにおニクもおいしかったし、おサシミもおいしかったし、私の作ったチョースーパーワサビトラップにひっかかったUさんの顔もサイコーだったしと、とても楽しいバーベQになったではないか。そしてエネルギー満タン!となった私たちは、明日に備えて眠るのだった。
7月30日、午前9時00分。とうとう紐差キャンプが始まった。このキャンプでのテーマは「ミサ」だった。今回は子供たちが中心となって、改めてミサの大切さを知るようにということで、このようなテーマを考えられたのだ。ミサとは何だ?それは私達の生活において、中心であり、かつ源である。だが私たちも人間だ。人間誰でもサボってしまったりと、マンネリ化というものがあるのだ。私自身そうである。だが今回のキャンプに参加して、私は目覚めた。ミサというものは知らない所からやってくるものではない。私たち自身が創りだし、私たち自身が呼び求めなければならないのだ。今回の子供たちのミサに対する情熱を見て、そう思った。子供たちの元気な声、若い心から学ぶことはたくさんあったのだ。その時歴史が動いた。
とうとう四日市志願院に帰って来てしまった。いや~しかし、やり残したことがたくさんありすぎて帰るのがホントに悔しかったなー。BGMとか・・・ミスった。ここで皆さん、人生は計画的に生きなければなりませんよ!ホントに。まーでもコレをバネに、レベルUPできるよう頑張るぜ!
そして、このキャンプでお世話になった方々、私達のためにいろいろと準備してくださった方々、本当にありがとうございます。このキャンプでたくさんの事を学び、私達に感動をあたえて下さったのは、いろいろな形で支えてくださった方々のおかげと言っても過言ではない。お礼に、ある先輩が言っていたことを私がうまい具合に盗んでアレンジしたものを紹介して、何か良いものを感じてもらえれば幸いである↓
この世の中は一つのパズルでできている
全てのピースが揃わなければ 一つのものは完成しない
一つのものを完成させるには 全てのピースが協力し合わなければならない
そしてすべてのピースが一つになったとき 神様の求める最高のものができるだろう
なぜなら
世界中のみなさん一人ひとりが 一つのピース(平和)でできているからだ
まぁ読んでください。今から、「私が勝手に作った皆さんの質問!第2弾!!」にお答えしましょう。この記事の題名に、「その時歴史が動いた」と書いてあるが、「全然歴史動いてないじゃん!」というツッコミを入れてくださるお方がいるのでは?まーいることにしよう!答え→何を言うか!プー!!私達はこのキャンプを通して学びそして、今この思い出をたくさんの人と分かち合う事によって、心の歴史が変化しているではないか!!!
|

